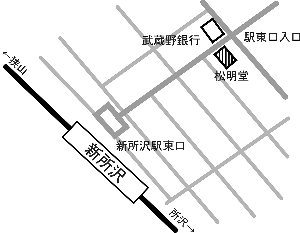リコーダーと通奏低音のセミナー
当セミナーの形態は受講者全員参加の公開レッスン形式ですが、より個人的な問題にも対応できるように、演奏も合わせて考えていきます。募集対象者は内容に興味をお持ちであれば、プロ、アマチュア、経験の有無、年齢は問いません。
♪通奏低音 リコーダー受講者による演奏を伴った上で、通奏低音受講者のレッスン時間を十分に取ります。特に旋律に応じた右手の付け方、およびバス声部の歌い方を重点的に指導します。
♪理論 実技の時間と深い関連性を持たせます。そのほか時代的な様式、作曲家作品研究などの幅広いテーマで授業を進めますが、一方的な解説に留まることなく可能な限り実践的授業をおこないます。
2 ご予約承りの電話、もしくはメールにて参加費、お振り込み先などをご連絡いたします。お振り込みは10日以内にお願いいたします。その期間が過ぎたときは、キャンセル扱いさせていただくことがあります。なお楽譜コピー代は当日実費にていただきます。
3 セミナー受講生になられた方は、次回講義の優先予約が可能となります。ただしその場合でも、正式なお申し込みは予約申込書、または予約問い合わせフォーム をご利用ください。
4 定員オーバーの時は、キャンセル待ち、次回同じテーマの講義の優先予約となります。ご了承ください。
参加費(2010年1月15日現在)
受講生 受講料1日 11500円(設備費を含む) 楽譜コピー代は実費(当日払い)
聴講生 聴講料1日 7000円 楽譜コピー代は実費(当日払い)
納入方法 受講テーマ回数分 指定日までに一括納入にてお願いいたします。セミナー当日は事務作業ができませんので、受講料、聴講料の現金でのお受け取り、および領収書の発行はできません。事前にお振り込みできるかどうか各自お確かめください。ただし、楽譜コピー代の実費については当日精算です。
参加費振込先 予約申し込み後、メールにてお知らせいたします。または郵送の予約申込書をご覧ください。
その他
申し込みの締め切りについて--定員はリコーダー10名程度、通奏低音5名程度とします。定員に達し次第締め切らせていただきます。
申し込み受付・優先順位--申し込み受付は先着順とします。この場合優先順位は電話予約の順番を優先します。口頭で次回以降のテーマへの参加希望を伝えた場合も、必ず事務局に予約問い合わせフォーム、メールもしくは電話予約をしてください。
キャンセル待ちについて--定員満席の場合は「キャンセル待ち」ができます。開講前にキャンセルが出た場合は、申し込み順で繰り上げます。
参加費などの返却について--申し込み後、振り込まれた受講料、聴講料については、当該テーマの開講日1週間前以降は返却できません。あらかじめご了承ください。
会場は松明堂音楽ホールです。
なお、、ホール・控え室内は飲食禁止です。ご了承ください。
359-0044 埼玉県所沢市松葉町17-5
Tel 0429-92-7667
松本マンション地下、詳しい地図はこちらから。