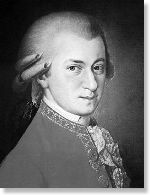2003年5月の演奏会プログラムノート 曲目
A Deux Clavier Fantasy フォルテピアノ・デュオ
W. F. バッハ
 J.S.バッハの長男です。次男のC.P.E.バッハが精力的に活動していたのとは対照的に、彼、W.F.バッハは悲憤にやつれ、芸術家としての大きな業績とか成功などといった望みもなく、悲劇によって暗くされた晩年を送り、挙げ句の果てに忘れ去られて貧困のうちになくなります。まさに絵に描いたような暗い人生なのですが、その原因とも言える彼の過度な感情の表出、均衡の欠如、精神的不安定さというものは、裏を返せばとてつもないファンタジーでもあったわけです。また、大バッハの音楽を編曲することもたびたびあったようで、今日の二台のクラヴィーアのための協奏曲もその一つと思われています。
J.S.バッハの長男です。次男のC.P.E.バッハが精力的に活動していたのとは対照的に、彼、W.F.バッハは悲憤にやつれ、芸術家としての大きな業績とか成功などといった望みもなく、悲劇によって暗くされた晩年を送り、挙げ句の果てに忘れ去られて貧困のうちになくなります。まさに絵に描いたような暗い人生なのですが、その原因とも言える彼の過度な感情の表出、均衡の欠如、精神的不安定さというものは、裏を返せばとてつもないファンタジーでもあったわけです。また、大バッハの音楽を編曲することもたびたびあったようで、今日の二台のクラヴィーアのための協奏曲もその一つと思われています。

C. P. E. バッハ
謹厳実直風な振りをして、そのくせ大変進取の気性に富んだ人物、J.S.バッハの次男坊です。当初フリードリッヒ大王の宮廷で鍵盤楽器を担当していました(左の絵でフルートを吹いているのがフリードリッヒ大王、後ろ向きにチェンバロを弾いているのがC.P.E.バッハ)。しかし懐古趣味の大王とはうまくいかず後にハンブルグに移ります。
彼はその有名な著書「正しいクラヴィーア奏法」の中でこう述べています。「力強いとか、楽しいとか言ったパッセージにおいても、奏者は自分自身をそれらのアフェクトの中に入れなければならない。しかも、常に変化し続ける感情を呼び起こさなければならない。奏者がもっとも良く聴衆の心をとらえるのはファンタジーによってである」と。いかにも、この多様な情緒を音楽的に表現することこそが彼の音楽なのです。
J. G. ミューテル
「しかしながら、非常にむら気の作曲家、ミューテルという名のすばらしい鍵盤楽器奏者をここリガでみつけました。彼は冬のしかも道路が深い雪で覆われた時だけ作曲をします。そうです、それ以外の時期は、馬車が通るときのガラガラという音に邪魔をされるからです。」
これは当時リガ(現在ラトビアの首都)に滞在していた、ヨハン・クリスチャン・ブランドの手記です。加えてもう一つ。 「私は今大変よい精神状態にあります。音楽の構想はすでにあり、その上霊感を出すための幸せな時間を持っているからです。というのも私は精神がそのような状態でない時に仕事をするのは好きではないし、この澄み切った精神状態は稀にしか起こらないのですから。常に作曲し続けているような人達は、知らず知らずのうちに己の精神を疲れさせてしまい自分自身をもなくしてしまっているのではないでしょうか。もし精神を回復させて新たな気持ちになれたなら、その人は新鮮かつ強力な方法で表現するはずです。つまらない眠たい作品は少なくなるに違いありません」。
これは、ミューテル本人が友人のエマニエル・バッハに送った手紙です。実に挑戦的であり当時としても自由で風変わりな発言ではありませんか。しかもそういうだけあって彼の残されている曲は、どれも一筋縄ではいかない、しかも珠玉の名作と呼びたくなるものばかりです。とりわけ、今日演奏する二台のクラヴィーアのためのソナタは大傑作です。当時ですら知る人ぞ知る存在であったミューテルは、今でもJ.S.バッハ最後の弟子としてしか認識されていません(彼のポートレートもあるらしいのですが手に入りませんでした)。ひとえに彼の寡作のためであると思えますが、常人離れした生活ポリシーも影響していることでしょう。
J. F. ハイドン
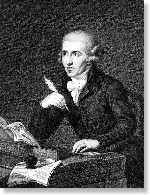 C.P.E.バッハの最も正統的な後継者を自他共に認めていたのが、ハイドンです。生存中に直接的な交流があったかどうかは定かではありませんが、影響を受けていたのは明らかです。ハイドンの友人かつ伝記作者のグリージンガーはC.P.E.バッハの初期のソナタを手に入れた若かりし頃のハイドン自身の言葉を残しています。「私はこれらの曲をすべて弾いてしまうまでは、クラヴィーアから離れることができませんでした。私のことをよく知っている人は、私が多くのことをC.P.E.バッハから学び、彼を理解し、熱心に勉強したことをわかってもらえるでしょう」。
それに対して、グリージンガーとほぼ同時期にハイドン伝を著したエステルハージの宮廷画家ディースは、C.P.E.バッハの言葉をあげています。 「ハイドンは私の著書を完全に把握し、それを役立てる事を心得ている唯一の人物だ」と。
今日演奏するのは、自筆譜作曲年代1771年と言われている、ハイドンの数少ない短調のソナタです。規模が大きいので多くの演奏会で弾かれています。ところで、ハイドンは楽器に対してはかなり奥手だったようで、ごく標準のフォルテピアノを手に入れたのも、モーツァルトはおろかベートーヴェンよりも遅かったようです。それまではどうしていたかというと、左下の絵にあるようなスクエアー・ピアノと呼ばれているものか、チェンバロで作曲していたようです。しかし、そんなことはどうでも良いというぐらいこの曲はすばらしいです。
C.P.E.バッハの最も正統的な後継者を自他共に認めていたのが、ハイドンです。生存中に直接的な交流があったかどうかは定かではありませんが、影響を受けていたのは明らかです。ハイドンの友人かつ伝記作者のグリージンガーはC.P.E.バッハの初期のソナタを手に入れた若かりし頃のハイドン自身の言葉を残しています。「私はこれらの曲をすべて弾いてしまうまでは、クラヴィーアから離れることができませんでした。私のことをよく知っている人は、私が多くのことをC.P.E.バッハから学び、彼を理解し、熱心に勉強したことをわかってもらえるでしょう」。
それに対して、グリージンガーとほぼ同時期にハイドン伝を著したエステルハージの宮廷画家ディースは、C.P.E.バッハの言葉をあげています。 「ハイドンは私の著書を完全に把握し、それを役立てる事を心得ている唯一の人物だ」と。
今日演奏するのは、自筆譜作曲年代1771年と言われている、ハイドンの数少ない短調のソナタです。規模が大きいので多くの演奏会で弾かれています。ところで、ハイドンは楽器に対してはかなり奥手だったようで、ごく標準のフォルテピアノを手に入れたのも、モーツァルトはおろかベートーヴェンよりも遅かったようです。それまではどうしていたかというと、左下の絵にあるようなスクエアー・ピアノと呼ばれているものか、チェンバロで作曲していたようです。しかし、そんなことはどうでも良いというぐらいこの曲はすばらしいです。
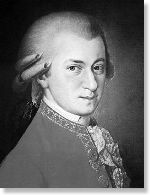
W. A. モーツアルト
モーツアルト・・・、あまりにも有名ですのでへたなことは書けません。とりあえず二台ピアノとモーツアルトについてご紹介しましょう。 現代において二台のフォルテピアノのための演奏会を企画するのは大変ですが、モーツアルト当時でもおいそれとはできなかったと思われます。ピアノと共に生きたモーツアルトですら、二台のための曲は僅かです。ソナタ、協奏曲、フーガなどすべて合わせても三曲しか現存していません(断片は除いて)。またそれらは断片も含めてすべて1781年から1783年の間にウィーンで書かれ、しかも、その現存する三曲のうち二曲(ソナタと協奏曲)は、弟子のアウエルンハンマー嬢(オーストリアの実業家アウエルンハンマー氏の令嬢ヨゼファ)を相方にして1781年11月23日のアウエルンハンマー邸での音楽会で演奏されています。ちなみにヨゼファ(1758-1820)はハイドンにも高く評価され、ウィーンでピアニストとして活躍した人らしいです。聞くところによると、モーツアルトに恋心を抱いていたようですが、モーツアルト本人は鼻っから相手にしていなかったとか・・・。コンスタンツェにぞっこんだった当時の彼(1782年に結婚)にしてみれば致し方ないことでもありますが。
蛇足ですが、先程述べた二台のための曲の断片というのは、実はコンスタンツェのためのものだったりします。これに限らず、奥さんのために書かれた曲の多くは未完のものが多いですね。完成していれば傑作になったであろうものも少なからずあるようです。
佐藤 裕一

 J.S.バッハの長男です。次男のC.P.E.バッハが精力的に活動していたのとは対照的に、彼、W.F.バッハは悲憤にやつれ、芸術家としての大きな業績とか成功などといった望みもなく、悲劇によって暗くされた晩年を送り、挙げ句の果てに忘れ去られて貧困のうちになくなります。まさに絵に描いたような暗い人生なのですが、その原因とも言える彼の過度な感情の表出、均衡の欠如、精神的不安定さというものは、裏を返せばとてつもないファンタジーでもあったわけです。また、大バッハの音楽を編曲することもたびたびあったようで、今日の二台のクラヴィーアのための協奏曲もその一つと思われています。
J.S.バッハの長男です。次男のC.P.E.バッハが精力的に活動していたのとは対照的に、彼、W.F.バッハは悲憤にやつれ、芸術家としての大きな業績とか成功などといった望みもなく、悲劇によって暗くされた晩年を送り、挙げ句の果てに忘れ去られて貧困のうちになくなります。まさに絵に描いたような暗い人生なのですが、その原因とも言える彼の過度な感情の表出、均衡の欠如、精神的不安定さというものは、裏を返せばとてつもないファンタジーでもあったわけです。また、大バッハの音楽を編曲することもたびたびあったようで、今日の二台のクラヴィーアのための協奏曲もその一つと思われています。
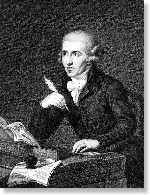 C.P.E.バッハの最も正統的な後継者を自他共に認めていたのが、ハイドンです。生存中に直接的な交流があったかどうかは定かではありませんが、影響を受けていたのは明らかです。ハイドンの友人かつ伝記作者のグリージンガーはC.P.E.バッハの初期のソナタを手に入れた若かりし頃のハイドン自身の言葉を残しています。「私はこれらの曲をすべて弾いてしまうまでは、クラヴィーアから離れることができませんでした。私のことをよく知っている人は、私が多くのことをC.P.E.バッハから学び、彼を理解し、熱心に勉強したことをわかってもらえるでしょう」。
それに対して、グリージンガーとほぼ同時期にハイドン伝を著したエステルハージの宮廷画家ディースは、C.P.E.バッハの言葉をあげています。 「ハイドンは私の著書を完全に把握し、それを役立てる事を心得ている唯一の人物だ」と。
今日演奏するのは、自筆譜作曲年代1771年と言われている、ハイドンの数少ない短調のソナタです。規模が大きいので多くの演奏会で弾かれています。ところで、ハイドンは楽器に対してはかなり奥手だったようで、ごく標準のフォルテピアノを手に入れたのも、モーツァルトはおろかベートーヴェンよりも遅かったようです。それまではどうしていたかというと、左下の絵にあるようなスクエアー・ピアノと呼ばれているものか、チェンバロで作曲していたようです。しかし、そんなことはどうでも良いというぐらいこの曲はすばらしいです。
C.P.E.バッハの最も正統的な後継者を自他共に認めていたのが、ハイドンです。生存中に直接的な交流があったかどうかは定かではありませんが、影響を受けていたのは明らかです。ハイドンの友人かつ伝記作者のグリージンガーはC.P.E.バッハの初期のソナタを手に入れた若かりし頃のハイドン自身の言葉を残しています。「私はこれらの曲をすべて弾いてしまうまでは、クラヴィーアから離れることができませんでした。私のことをよく知っている人は、私が多くのことをC.P.E.バッハから学び、彼を理解し、熱心に勉強したことをわかってもらえるでしょう」。
それに対して、グリージンガーとほぼ同時期にハイドン伝を著したエステルハージの宮廷画家ディースは、C.P.E.バッハの言葉をあげています。 「ハイドンは私の著書を完全に把握し、それを役立てる事を心得ている唯一の人物だ」と。
今日演奏するのは、自筆譜作曲年代1771年と言われている、ハイドンの数少ない短調のソナタです。規模が大きいので多くの演奏会で弾かれています。ところで、ハイドンは楽器に対してはかなり奥手だったようで、ごく標準のフォルテピアノを手に入れたのも、モーツァルトはおろかベートーヴェンよりも遅かったようです。それまではどうしていたかというと、左下の絵にあるようなスクエアー・ピアノと呼ばれているものか、チェンバロで作曲していたようです。しかし、そんなことはどうでも良いというぐらいこの曲はすばらしいです。