2002年10月の演奏会プログラムノート 曲目
Endeavour on Bach チェンバロ・フォルテピアノリサイタル
汲めども尽きぬ泉とは使い古された表現ですが、まさにバッハのためにあるような言葉です。300年以上たった今でも、無限の可能性を提供してくれるのですから、驚きと言うほかありません。今回の「チェンバロとフォルテピアノでバッハを弾こう」という少々無謀な試みも、バッハの音楽が持つ懐の深さが可能にしてくれた賜です。
ところで、バッハとフォルテピアノの結びつきは、歴史的には大変あやふやです。少なくとも2回から3回くらいは出会っているようです。ちなみにアグリーコラによれば、(1732年以降のいつか)フライブルクに工房を持つゴットフリート・ジルバーマン(オルガン製作者)は試作した2台のうちの1台のフォルテピアノをバッハに試奏してもらったということです。そのときのバッハの評価は「高音が良くならない、弾きにくい」というものであったらしく、自分の楽器にケチを付けられるのを大変嫌がるのを常としたジルバーマンは少々おかんむりだったようです。しかし、後日発憤して改良した楽器に対してはバッハから高い評価をもらえたと言います。ただし、それがいつのことであったのかは記述がありません。
 次の資料は、1733年のものです。バッハはライプツィヒのツィンマーマンの庭園で毎週「コレギウム・ムジクム」として有名なコーヒーコンサートを行っていましたが、1733年6月16日のときの広告に「ジルバーマンの作った新式のクラヴィーアでのコンサート」とあります。この新式のクラヴィーアというのがおそらくフォルテピアノのことであろうというのが、おおかたの見解のようです。これもきわめて確かじゃありませんが・・。最後の資料は最も確実性の高いものです。フォルケルがバッハの長男フリーデマン・バッハから聞いたという話です。1747年、バッハがベルリン(もしくはポツダム)にフリードリヒ大王を訪問したさい、そこでジルバーマン会心のフォルテピアノで「大王のテーマ」による即興演奏をした、という例の話です。その楽器はバッハによって高い評価を受けたそうですが。
いずれにしても、これだけでバッハがフォルテピアノを知っていたと断定するのはどうでしょうか。普通なら知らないに等しい、と言ってしまっても良さそうな経験値です。もちろん、バッハと私達を同列に考えるような不遜なことはできませんが、それにしても「高い評価」の基準とは一体どこにあったのでしょう? おまけに触ったのはジルバーマンの楽器だけ、と言うのも少し問題です。何が問題かというと、思いっきり寄り道になる上、いささか専門的な内容で恐縮ですが、この際言ってしまいましょう。
次の資料は、1733年のものです。バッハはライプツィヒのツィンマーマンの庭園で毎週「コレギウム・ムジクム」として有名なコーヒーコンサートを行っていましたが、1733年6月16日のときの広告に「ジルバーマンの作った新式のクラヴィーアでのコンサート」とあります。この新式のクラヴィーアというのがおそらくフォルテピアノのことであろうというのが、おおかたの見解のようです。これもきわめて確かじゃありませんが・・。最後の資料は最も確実性の高いものです。フォルケルがバッハの長男フリーデマン・バッハから聞いたという話です。1747年、バッハがベルリン(もしくはポツダム)にフリードリヒ大王を訪問したさい、そこでジルバーマン会心のフォルテピアノで「大王のテーマ」による即興演奏をした、という例の話です。その楽器はバッハによって高い評価を受けたそうですが。
いずれにしても、これだけでバッハがフォルテピアノを知っていたと断定するのはどうでしょうか。普通なら知らないに等しい、と言ってしまっても良さそうな経験値です。もちろん、バッハと私達を同列に考えるような不遜なことはできませんが、それにしても「高い評価」の基準とは一体どこにあったのでしょう? おまけに触ったのはジルバーマンの楽器だけ、と言うのも少し問題です。何が問題かというと、思いっきり寄り道になる上、いささか専門的な内容で恐縮ですが、この際言ってしまいましょう。
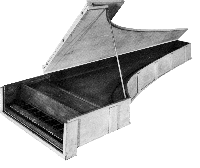 ゴットフリート・ジルバーマンは確かに個性的な鍵盤楽器製作者です。チェンバル・ダムールなるユニークなクラヴィコードを発明したり、バッハには必ずしも良い評価をされなかったとはいえ、本業のオルガン製作も当時の社会一般では高い評価を得ていたようです。しかるにフォルテピアノに関しては少々過大評価されている感があります。彼の最初のピアノ(1732年頃)は、楽器についてはほとんど素人と思える人によるクリストーフォリの初期のピアノ(1709年頃)の紹介文---言ってみれば雑誌記者の取材記事です---を元にして作った、どう贔屓目に見ても大変いい加減なコピーになったであろう代物でした。後に奮起して作ったとされる「ジルバーマン会心のフォルテピアノ」(1747年バッハが弾いたもの)は、間違いなくクリストーフォリ後期のピアノ(1726年頃)の実物を参考にして再構成したコピー、しかもピアノの音色や音量にとって大変重要なアタッキング・ポイント(打弦点)については考えが及ばなかったのか、大変不備なコピーになっています。ポリシーを欠いたコピーが本物を凌駕することはあり得ません。楽器製作者としての努力をすることなく作り上げてしまった「ジルバーマン会心のフォルテピアノ」は明らかに過大評価なわけです。とはいえ、その後シュタインに及ぼした影響という点については十分に評価できるのですが・・・。
ゴットフリート・ジルバーマンは確かに個性的な鍵盤楽器製作者です。チェンバル・ダムールなるユニークなクラヴィコードを発明したり、バッハには必ずしも良い評価をされなかったとはいえ、本業のオルガン製作も当時の社会一般では高い評価を得ていたようです。しかるにフォルテピアノに関しては少々過大評価されている感があります。彼の最初のピアノ(1732年頃)は、楽器についてはほとんど素人と思える人によるクリストーフォリの初期のピアノ(1709年頃)の紹介文---言ってみれば雑誌記者の取材記事です---を元にして作った、どう贔屓目に見ても大変いい加減なコピーになったであろう代物でした。後に奮起して作ったとされる「ジルバーマン会心のフォルテピアノ」(1747年バッハが弾いたもの)は、間違いなくクリストーフォリ後期のピアノ(1726年頃)の実物を参考にして再構成したコピー、しかもピアノの音色や音量にとって大変重要なアタッキング・ポイント(打弦点)については考えが及ばなかったのか、大変不備なコピーになっています。ポリシーを欠いたコピーが本物を凌駕することはあり得ません。楽器製作者としての努力をすることなく作り上げてしまった「ジルバーマン会心のフォルテピアノ」は明らかに過大評価なわけです。とはいえ、その後シュタインに及ぼした影響という点については十分に評価できるのですが・・・。
さてさてとんでもなく寄り道してしまいましたが、兎に角、このような状況を理解した上でそれにもかかわらず、今回の音楽会に敢えてバッハをフォルテピアノで演奏する、と言うプログラムを加えたのは、実はこのような歴史的背景とはまったく関係のないことが元になっています。って、じゃあ今までのとんでもなく長い前置きはいったい何だったんだ、と言うおしかりを受けそうですが・・・。
その前置きに比べると感動的に大変に短く、呆然とするほど単純な理由があります。過去何回か行ってきたチェンバロとフォルテピアノによる音楽会で、ピアニッシモを要求する音楽にはフォルテピアノ(もしくはクラヴィコード)が大変に効果的であること、それはバッハにも充分に当てはまることに気がついてしまった、と言うのがその理由です。オーセンティシィティーも重要だけど、それ以上に音楽性が大事と言うことでしょうか。
加えて、フォルテピアノで演奏する3曲のうち2曲は一般的な鍵盤楽曲ではありません。一つは無伴奏ヴァイオリンパルティータからの大変有名なシャコンヌ。これはブゾーニを筆頭に古今東西著名な方々が競ってピアノ用に編曲しています。今回は新たにフォルテピアノ用に編曲したものを演奏いたします。無伴奏ヴァイオリン曲については鍵盤楽器との関わりにおいて少しばかり歴史的背景もあります。1775年、アグリーコラによるバッハの無伴奏ヴァイオリン曲の記述によりますと、バッハ自身がそれらの曲を必要と思われる和声を加えてクラヴィコードで弾いていた、と言うことです。より強く響きとしての和声を求めていたと考えることもできるかと思います。
もう一つは六声のリチェルカーレ。1747年のベルリン訪問時、大王の要望に応えたという作曲の経緯を見れば確かに鍵盤楽曲だったのですが、現実的にはそうではなく捉えられることが多い曲です。怖れ多くも言ってみれば、フォルテピアノによる鍵盤楽曲としての再認識、と言うことになりましょうか。ポリフォニーの仮面をかぶったファンタジックな曲であることが、フォルテピアノを通してお伝えできれば幸いです。
さて、紙面もだいぶ少なくなってきたところで今日のコンサートのチェンバロ曲とは直接の関係はありませんが、バッハとチェンバロについても少しお話しいたしましょう。実はバッハとの関わりはフォルテピアノとは異なる意味で、これまた殊の外あやふやなのです。もちろんバッハはチェンバロを数台所有していましたし、常に弾いていたと思います。しかし、どんな楽器を好んだか、チェンバロという楽器に対して何を考えていたか、になると未だ闇の中です。
近年採り上げられる機会が増えたものに、ベルリンのミートケの楽器がありますが、これはケーテン宮廷のためバッハ自らがベルリンまで買い出しに行ったもの。ブランデンブルク協奏曲第5番の初演はこの楽器で行われたことが知られています。ただその後、バッハが自分のためにミートケを所有したという記録はありません。またバッハの遺産目録に大型のチェンバロが記されていますが、これはおそらく、テューリンゲン地方、エルフルトの南50㎞ほどのところにあるグロス・ブライテンバッハ在住のハラスによるとされている手鍵盤16フィート付楽器です。ハラスはアイゼナッハのバッハ家とは親戚付き合いをしていたとも言われており、言うなれば情実人事ならぬ情実楽器であった可能性もあります。バッハが長男のヴィルヘルム・フリーデマンに与えたものとも言われており、実物と思われるものがベルリンの楽器博物館に現存しています。これが最近になってぶり返してきたかのように注目されていますが、どうもいかがわしい。ミートケ・ブームのあとにハラス・ブームを作ろうとしている楽器製作者の陰謀ともとれます。まあ、そのへんのことは置いておいて、いずれにせよこの2台だけがバッハと関わった名前が判明しているチェンバロになりますが、バッハ自身がチェンバロに与えた評価というものはこの2台以外を含めても何一つ存在していません。だからといって、バッハがまったく鍵盤楽器の評価をしなかったのかというと、そんなことはないのです。
オルガンに関して言えば、第二次世界大戦で当時の楽器はなくなってしまいましたがハンブルクの聖カタリナ教会のオルガンを最も良いものとしてあげています。加えて、「コルネ」というレジストレーションを好んで使用していたこともわかっています。また、ラウテン・クラヴィーアというチェンバロの金属弦の替わりにガット弦を張った楽器を、記録上は2台特注で作ってもらっています。双方に共通しているのは「まるい音」で、どちらかというと人の声に近い音を好んでいたと言うことは考えられます。どうもここら辺にバッハの基準らしきものがあるような気がするのですが、いかがでしょうか。何ともとりとめのないノートになってしまいましたが、バッハの将来にはまだまだ可能性があることが感じられただけでも大収穫だと思っています。
佐藤 裕一
コンサートに寄せて
 ついに当日になってしまいました。家出でもしようか? かっこよく駆け落ちでも? と思惑する毎日がここしばらく続いていたような気がします。といっても家出するにもその先の当てがないし、駆け落ちするにも適当なよい相手がいない、おまけに歳が歳だし・・これではかっこよくとはいかないなあ。
ついに当日になってしまいました。家出でもしようか? かっこよく駆け落ちでも? と思惑する毎日がここしばらく続いていたような気がします。といっても家出するにもその先の当てがないし、駆け落ちするにも適当なよい相手がいない、おまけに歳が歳だし・・これではかっこよくとはいかないなあ。
何回もリサイタルをしているのに今回に限って何故か直前になって頭痛が続くわ、ついには親不知もむくむくと出てくるわでなんだか変だぞ。そうだ!、バッハだからいけなかったのだ・・・と気づくのが遅すぎました。
やはりバッハはとても怖いです。それに加えて、この企画を考えたのはおよそ2年ほど前、考え始めた時点ではあれも弾きたいこれも弾きたい、こっちもいいかな?状態で、ヨシッ!と決めてしまったのですが、いざ、だんだんコンサートが近づくにつれて、あややっ!、しまったかも・・と思うのですね。そんなわけで今日はとにかく、私も、そして聴きに来て下さっている皆様も、大変な緊張状態に置かれるであろうと推察されますが、最後までどうぞおつきあいください。無事お家にお帰りになられたら、上等の食後酒で余韻を楽しんでいただければ幸いです。
岩淵 恵美子

 次の資料は、1733年のものです。バッハはライプツィヒのツィンマーマンの庭園で毎週「コレギウム・ムジクム」として有名なコーヒーコンサートを行っていましたが、1733年6月16日のときの広告に「ジルバーマンの作った新式のクラヴィーアでのコンサート」とあります。この新式のクラヴィーアというのがおそらくフォルテピアノのことであろうというのが、おおかたの見解のようです。これもきわめて確かじゃありませんが・・。最後の資料は最も確実性の高いものです。フォルケルがバッハの長男フリーデマン・バッハから聞いたという話です。1747年、バッハがベルリン(もしくはポツダム)にフリードリヒ大王を訪問したさい、そこでジルバーマン会心のフォルテピアノで「大王のテーマ」による即興演奏をした、という例の話です。その楽器はバッハによって高い評価を受けたそうですが。
いずれにしても、これだけでバッハがフォルテピアノを知っていたと断定するのはどうでしょうか。普通なら知らないに等しい、と言ってしまっても良さそうな経験値です。もちろん、バッハと私達を同列に考えるような不遜なことはできませんが、それにしても「高い評価」の基準とは一体どこにあったのでしょう? おまけに触ったのはジルバーマンの楽器だけ、と言うのも少し問題です。何が問題かというと、思いっきり寄り道になる上、いささか専門的な内容で恐縮ですが、この際言ってしまいましょう。
次の資料は、1733年のものです。バッハはライプツィヒのツィンマーマンの庭園で毎週「コレギウム・ムジクム」として有名なコーヒーコンサートを行っていましたが、1733年6月16日のときの広告に「ジルバーマンの作った新式のクラヴィーアでのコンサート」とあります。この新式のクラヴィーアというのがおそらくフォルテピアノのことであろうというのが、おおかたの見解のようです。これもきわめて確かじゃありませんが・・。最後の資料は最も確実性の高いものです。フォルケルがバッハの長男フリーデマン・バッハから聞いたという話です。1747年、バッハがベルリン(もしくはポツダム)にフリードリヒ大王を訪問したさい、そこでジルバーマン会心のフォルテピアノで「大王のテーマ」による即興演奏をした、という例の話です。その楽器はバッハによって高い評価を受けたそうですが。
いずれにしても、これだけでバッハがフォルテピアノを知っていたと断定するのはどうでしょうか。普通なら知らないに等しい、と言ってしまっても良さそうな経験値です。もちろん、バッハと私達を同列に考えるような不遜なことはできませんが、それにしても「高い評価」の基準とは一体どこにあったのでしょう? おまけに触ったのはジルバーマンの楽器だけ、と言うのも少し問題です。何が問題かというと、思いっきり寄り道になる上、いささか専門的な内容で恐縮ですが、この際言ってしまいましょう。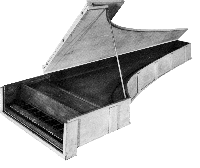 ゴットフリート・ジルバーマンは確かに個性的な鍵盤楽器製作者です。チェンバル・ダムールなるユニークなクラヴィコードを発明したり、バッハには必ずしも良い評価をされなかったとはいえ、本業のオルガン製作も当時の社会一般では高い評価を得ていたようです。しかるにフォルテピアノに関しては少々過大評価されている感があります。彼の最初のピアノ(1732年頃)は、楽器についてはほとんど素人と思える人によるクリストーフォリの初期のピアノ(1709年頃)の紹介文---言ってみれば雑誌記者の取材記事です---を元にして作った、どう贔屓目に見ても大変いい加減なコピーになったであろう代物でした。後に奮起して作ったとされる「ジルバーマン会心のフォルテピアノ」(1747年バッハが弾いたもの)は、間違いなくクリストーフォリ後期のピアノ(1726年頃)の実物を参考にして再構成したコピー、しかもピアノの音色や音量にとって大変重要なアタッキング・ポイント(打弦点)については考えが及ばなかったのか、大変不備なコピーになっています。ポリシーを欠いたコピーが本物を凌駕することはあり得ません。楽器製作者としての努力をすることなく作り上げてしまった「ジルバーマン会心のフォルテピアノ」は明らかに過大評価なわけです。とはいえ、その後シュタインに及ぼした影響という点については十分に評価できるのですが・・・。
ゴットフリート・ジルバーマンは確かに個性的な鍵盤楽器製作者です。チェンバル・ダムールなるユニークなクラヴィコードを発明したり、バッハには必ずしも良い評価をされなかったとはいえ、本業のオルガン製作も当時の社会一般では高い評価を得ていたようです。しかるにフォルテピアノに関しては少々過大評価されている感があります。彼の最初のピアノ(1732年頃)は、楽器についてはほとんど素人と思える人によるクリストーフォリの初期のピアノ(1709年頃)の紹介文---言ってみれば雑誌記者の取材記事です---を元にして作った、どう贔屓目に見ても大変いい加減なコピーになったであろう代物でした。後に奮起して作ったとされる「ジルバーマン会心のフォルテピアノ」(1747年バッハが弾いたもの)は、間違いなくクリストーフォリ後期のピアノ(1726年頃)の実物を参考にして再構成したコピー、しかもピアノの音色や音量にとって大変重要なアタッキング・ポイント(打弦点)については考えが及ばなかったのか、大変不備なコピーになっています。ポリシーを欠いたコピーが本物を凌駕することはあり得ません。楽器製作者としての努力をすることなく作り上げてしまった「ジルバーマン会心のフォルテピアノ」は明らかに過大評価なわけです。とはいえ、その後シュタインに及ぼした影響という点については十分に評価できるのですが・・・。 ついに当日になってしまいました。家出でもしようか? かっこよく駆け落ちでも? と思惑する毎日がここしばらく続いていたような気がします。といっても家出するにもその先の当てがないし、駆け落ちするにも適当なよい相手がいない、おまけに歳が歳だし・・これではかっこよくとはいかないなあ。
ついに当日になってしまいました。家出でもしようか? かっこよく駆け落ちでも? と思惑する毎日がここしばらく続いていたような気がします。といっても家出するにもその先の当てがないし、駆け落ちするにも適当なよい相手がいない、おまけに歳が歳だし・・これではかっこよくとはいかないなあ。