それはさておき、以前(おそらく1733年)、ゴットフリート・ジルバーマン -Gottfried Silbermann-(1683-1753)が試作したフォルテピアノにけちを付けて以来と思われるが、この1747年の謁見のときにJ.S.バッハはジルバーマン会心のできたてフォルテピアノを弾いている。(ただし、このバッハとジルバーマンの時間的場所的事実関係は明確になっていない。) 思えば、新進のフォルテピアノを、最終的にはサンスーシ宮殿、シャルロッテンブルク宮殿などと併せて15台(J.N.フォルケルの手記による、かなり誇大表示だと思われるが少なくとも3台以上)も購入したフリードリヒⅡ世は、その真意は計りがたいもののなかなか大したものである。ちなみに、戦火を逃れたフリードリヒⅡ世所有だったジルバーマン・フォルテピアノ(1746年製)が今もサンスーシにある。演奏可能かどうかは残念ながらわからない。
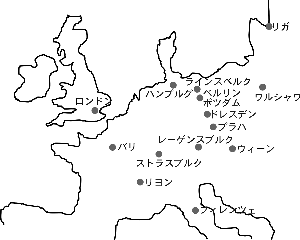 国王の離宮に対する思い入れは、音楽に対するものだけではもちろんない。新旧取り混ぜた彫刻5000体、ルーベンス、ヴァン・ダイク、コレッジョ、ラファエロ、ダ・ヴィンチ、ティッツィアーノらの絵画、哲学、文学などの図書などに出費を惜しまなかった。さて、この芸術に目がなかった国王だが、父王フリードリヒ・ヴィルヘルムⅠ世(1688-1740)生存中は、王は富国強兵を主義として芸術にはまったく関心を示さなかったため、なかなか大変だった。事あるごとに対立したこの親子は、結局別居という形を取ることになる。1736年より1740年父王が亡くなるまで、フリードリヒはベルリンの北70キロの所にあるラインスベルク城に蟄居してしまうのである。そしてラインスベルク城において、音楽、哲学、文学、美術三昧の生活を送る。なかなか大変とはいえ羨ましくもある。
国王の離宮に対する思い入れは、音楽に対するものだけではもちろんない。新旧取り混ぜた彫刻5000体、ルーベンス、ヴァン・ダイク、コレッジョ、ラファエロ、ダ・ヴィンチ、ティッツィアーノらの絵画、哲学、文学などの図書などに出費を惜しまなかった。さて、この芸術に目がなかった国王だが、父王フリードリヒ・ヴィルヘルムⅠ世(1688-1740)生存中は、王は富国強兵を主義として芸術にはまったく関心を示さなかったため、なかなか大変だった。事あるごとに対立したこの親子は、結局別居という形を取ることになる。1736年より1740年父王が亡くなるまで、フリードリヒはベルリンの北70キロの所にあるラインスベルク城に蟄居してしまうのである。そしてラインスベルク城において、音楽、哲学、文学、美術三昧の生活を送る。なかなか大変とはいえ羨ましくもある。フリードリヒⅡ世の宮廷楽団は、およそこの時代にほとんどできあがっていたようだ。有名な人をあげてみると、ヴァイオリンのヨハン・ゴットリープ・グラウン 、その弟カール・ハインリヒ・グラウン。ボヘミアのフランツ・ベンダ、その弟ヨハン・ベンダ、ゲオルク・アントン・ベンダ 。そして、鍵盤楽器のC.P.E.バッハ など、1738年当時で17名という。加えて、1728年以来(フリードリヒ16歳の頃)フルートのレッスンを受けているドレスデンのヨハン・ヨアヒム・クヴァンツは1741年に宮廷フルーティストとしてこの楽団に迎えられている。いやはや、それにしても何とも贅沢なオーケストラである。当時ここに匹敵する宮廷楽団はそう多くはなかったのではないだろうか。
確かにこの宮廷楽団の面々は、フリードリヒⅡ世本人を除けば、演奏技術においてもこの上なく優秀だと思われる。しかし、各人の主張するところの方向性は、2つに分かれていたようである。一つは、フリードリヒⅡ世やクヴァンツ、グラウン兄弟が言うところの「良い趣味」を求めている一派。多分にロココ趣味であり、軽妙洒脱、優雅を好むように見える。いわゆる予定調和の世界である。もう一つは、C.P.E.バッハやベンダ兄弟が求めているところの、即興性による感情の劇的表現である。これはまさに予測不可能の世界である。この違いはかなり決定的だったようで、フリードリヒⅡ世やクヴァンツにはC.P.E.バッハたちの音楽はあまり気に入ってはいなかったようだ。クヴァンツの年俸がC.P.E.バッハのそれの7倍近くあったことを見ても、また後から入ってきた第二チェンバロ奏者のニッヒェルマンですら彼の2倍の給料だったということからも、それは明らかであると思うがどうか。
|
名前 |
出身 |
生没年・入団 |
役職・担当楽器 |
専門 |
| ヨハン・ゴットリープ・グラウン Johann Gottlieb Graun |
ヴァーレンブリュック | (1702-1771) 1732 | 1732コンサート・マスター ヴァイオリン | ヴァイオリン |
| カール・ハインリヒ・グラウン Carl Heinrich Graun |
ヴァーレンブリュック | (1703-1759) 1735 | 1735楽長 ヴァイオリン | オペラ |
| フランツ・ベンダ Franz (Frantisek) Benda |
ベナートキープラハ近郊 | (1709-1786) 1733 | 1771コンサート・マスター ヴァイオリン | ヴァイオリン |
| ヨハン・ベンダ Johann Benda |
ベナートキープラハ近郊 | (1713-1752) | ヴァイオリン | ヴァイオリン |
| ゲオルク・アントン・ベンダ Georg (Jiri Antonin) Benda |
ベナートキープラハ近郊 | (1722-1795) | ヴァイオリン | オペラ |
| C.P.E.バッハ Carl Philipp Emanuel Bach |
ヴァイマール | (1714-1788) 1738 | 第一チェンバロ奏者 鍵盤 | オペラ、鍵盤 |
| ヨハン・ヨアヒム・クヴァンツ Johann Joachim Quantz |
ゲッティンゲン近郊 | (1697-1773) 1741 | フルート | フルート |
| フリードリヒⅡ世 Friedrich II |
ベルリン | (1712-1786) | フルート |
イギリスの音楽史家チャールズ・バーニー(1726-1814)によれば、「プロイセンの宮廷音楽家の中で、C.P.E.バッハとフランツ・ベンダだけが独自の道を歩む勇気を持っていた。・・・クヴァンツやグラウンとことなる趣味を目指すものは迫害された。」ということになるが、事実、C.P.E.バッハは1768年にハンブルグへと去ってゆく。
ただし、彼がベルリンを離れる理由はフリードリヒⅡ世との不仲だけではなかった。フリードリヒⅡ世は確かに音楽を好み、また音楽文化を援護したとも思うが、それと同じくらい戦争が好きだった。度重なるオーストリアとの戦争で、国土を荒廃させてもいる。G.ジルバーマンにより発展の兆しを見せたフォルテピアノも、後に続く製作者たちは戦争を避けてその多くがロンドンに移ってしまい、イギリスのフォルテピアノ文化に貢献することになる。また、ごく一部はバイエルンのレーゲンスブルク、アルザスのストラスブルクなどを経て、最終的にはウィーンのフォルテピアノ文化として発展する。ベルリン、プロイセンから音楽を遠ざけたのもまたフリードリヒⅡ世本人だったのである。
なんにせよ、今回の演奏はサンスーシ宮殿においては迫害される可能性が大変高い。週に3回以上開催されたというフリードリヒⅡ世の宮廷音楽会でこのようなプログラムが組まれることはまず有り得ない。期待に反する和声進行と、多種多様なテンポはフリードリヒⅡ世を困惑させるのに充分であろう。それほど彼らの音楽は、即興的で、劇的感情表現に満ち、かつまた幻想的である。「音楽というものはまず第一に心に触れるものでなくてはならない。」とするC.P.E.バッハの音楽感は時間を超えて共鳴しうると思う。幻のサンスーシ宮廷音楽会、楽しんでもらえれば幸いである。
コンサートに寄せて

このところ、特定された場所で何回も行われたコンサートに興味を持っている。昨年はロンドンのヴォクスホールでの音楽会、今回のサンスーシ、と続けてこの種のコンサートを企画してきた。そしてそれらのプログラムを考えているとき、そこに生きていた音楽家 、聴衆、王様、女王様、そしてそこに入り乱れていたはずの様々な人間模様が手に取るように見えてくるのはとても楽しいものである。音楽的興味としては、やはり「ファンタジア」ではないだろうか。それについて感じたことを少し書いてみたい。
ファンタジアに最も必要なのは言葉を伝えるセンスである。最近おこがましくも、歌を志す生徒たちのレッスンをしていて思うことだが、歌には言葉があるので「伝えたいこと」は割とはっきりしている。もっとも、そのために様々の努力はしているのだけれど、楽器と比べると直接的であると思う。そこで、だからこそ楽器奏者は楽しめるのである。いかにして音を言葉にするか。ファンタジアはもってこいの材料である。プログラムの最後に演奏するのファンタジアは、以前のリサイタルでも言葉にするのに苦労した。なんと今回はそれを2人ですることになってしまった。毎日山のように言葉を作り続けている。リサイタルの後はさぞかし雄弁家になっているであろう。(もう充分という声も聞こえますが。)
 プロイセン王フリードリヒⅡ世
プロイセン王フリードリヒⅡ世
