1999年1月の演奏会プログラムノート 曲目
フルートとフォルテピアノによる18世紀音楽の悦楽
「音楽の目的は人を魅了し、感動させることである。そのために用いる様々な手段がある。フォルテ、ピアノ、レガート、スタッカート、音の持続、掛留など感情を込めて弾くのに役立つあらゆるものがそれである。」これは今日のプログラムにも登場するクレメンティが、「ピアノ演奏への手引き」(1801年)の中で述べていることですが、まったくもってその通りだと思いますし、おおよそ自明なことでもあります。ではなぜこのようなことから書き出したかと言いますと、少々弁解じみてはいますが、今日のプログラムはオーセンティックな見地から見た場合かなり冒険的な試みなのです。具体的に言いましょう。たとえばミューテルですが、時間的、地域的といった彼の環境から考えて、おそらくフォルテピアノのために音楽を書いたことはないと思われます。C.P.E.バッハにしたところで事情は大して変わりません。彼はフォルテピアノを知っていたし、フォルテピアノのために音楽を書いてはいます。しかし彼が活躍していた頃のフォルテピアノはどうやらあまり彼を満足はさせなかったようで、通奏低音などでフォルテピアノを使うことは考えていなかったのではないかと思われます。そのことは彼自ら「正しいクラヴィーア奏法」の中で述べています。とどめは今日のハイドンです。よく弾かれる曲ですが作曲されたのは1771年、実を言いますとハイドンがまともな演奏会用のフォルテピアノをもっていた可能性はありません。あったとすれば小型のスクエアーピアノでしょう。ところが、と少々大げさですが、彼らは共通して彼らの多感様式的な音楽を実現させるために、限りないダイナミックス、ppからffまでの幅広いダイナミックスを重要な表現手段(先ほどのクレメンティも述べていますが)にしていたのも事実です。なんか矛盾したことを言っているようですが、彼ら音楽家の中ではこの矛盾はクラヴィコードというたぐいまれな鍵盤楽器を愛することで解消していたのではないかと考えられます。特にC.P.E.バッハなどは十分その気があります。要約し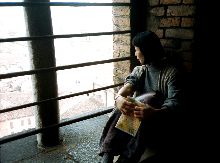 ますと、彼らは限りないダイナミックスを手段としたかった。鍵盤楽器としてクラヴィコードはその要求を十分に満たした。と言うことは、彼らはその効果というものをよくわかっていた。しかし実際の演奏の場では、特に他の旋律楽器と一緒に演奏するのはあまりの小さい音のため現実的ではなかった。かと言ってそのころのフォルテピアノはまだちょっと実用的ではなかった。結果、ダイナミックスの効果を十分意識して作曲をしたが、実際の演奏の場ではチェンバロを使用するのがその時点では最良の選択だった。そう、もうほんの10年か20年後なんですが、十分実用になるフォルテピアノが作られるようになるのは1780年代になってからといわれています。
さてようやく冒頭の「音楽の目的」に戻りますが、今回のこの私たちの「冒険的な試み」は今日のプログラムの「音楽の目的」に対する一つの方向だと思っています。またそれが良い方向になるだろうとも信じています。何しろ、フォルテピアノの通奏低音による演奏というのは困難を極めもしましたが、それにもましてリハーサルの度に新たな発見がありました。前述のクレメンティの「ピアノ演奏の手引き」の中に、「目的を追求して苦労したああとであらゆる困難を乗り越えそして輝かしい完成に達した生徒」の話がありますが、まさにその感がします。禅問答のようなプログラムノートになってしまいましたが、ここまで読んでいただいた方には大変感謝をいたします。また実際の演奏の時にはこんなことは全部忘れて音楽そのものを楽しんでいただければ幸いです。
ますと、彼らは限りないダイナミックスを手段としたかった。鍵盤楽器としてクラヴィコードはその要求を十分に満たした。と言うことは、彼らはその効果というものをよくわかっていた。しかし実際の演奏の場では、特に他の旋律楽器と一緒に演奏するのはあまりの小さい音のため現実的ではなかった。かと言ってそのころのフォルテピアノはまだちょっと実用的ではなかった。結果、ダイナミックスの効果を十分意識して作曲をしたが、実際の演奏の場ではチェンバロを使用するのがその時点では最良の選択だった。そう、もうほんの10年か20年後なんですが、十分実用になるフォルテピアノが作られるようになるのは1780年代になってからといわれています。
さてようやく冒頭の「音楽の目的」に戻りますが、今回のこの私たちの「冒険的な試み」は今日のプログラムの「音楽の目的」に対する一つの方向だと思っています。またそれが良い方向になるだろうとも信じています。何しろ、フォルテピアノの通奏低音による演奏というのは困難を極めもしましたが、それにもましてリハーサルの度に新たな発見がありました。前述のクレメンティの「ピアノ演奏の手引き」の中に、「目的を追求して苦労したああとであらゆる困難を乗り越えそして輝かしい完成に達した生徒」の話がありますが、まさにその感がします。禅問答のようなプログラムノートになってしまいましたが、ここまで読んでいただいた方には大変感謝をいたします。また実際の演奏の時にはこんなことは全部忘れて音楽そのものを楽しんでいただければ幸いです。
リサイタルによせて ハイドン ソナタ ハ短調
自筆譜作曲年代が確定している1771年の作品。ハイドンの数少ない短調のソナタであり、また規模が大きいので今日多くの演奏会で弾かれています。ハイドンは楽器に対してはかなり奥手だったようで、ごく標準のフォルテピアノを手に入れたのは、モーツァルトはおろかベートーヴェンよりも遅かったようです。しかし、そんなことはどうでも良いというぐらいこの曲はすばらしい。この曲の第2楽章に解説はいりません。
岩淵 恵美子

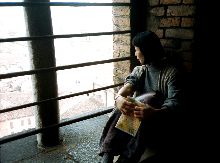 ますと、彼らは限りないダイナミックスを手段としたかった。鍵盤楽器としてクラヴィコードはその要求を十分に満たした。と言うことは、彼らはその効果というものをよくわかっていた。しかし実際の演奏の場では、特に他の旋律楽器と一緒に演奏するのはあまりの小さい音のため現実的ではなかった。かと言ってそのころのフォルテピアノはまだちょっと実用的ではなかった。結果、ダイナミックスの効果を十分意識して作曲をしたが、実際の演奏の場ではチェンバロを使用するのがその時点では最良の選択だった。そう、もうほんの10年か20年後なんですが、十分実用になるフォルテピアノが作られるようになるのは1780年代になってからといわれています。
さてようやく冒頭の「音楽の目的」に戻りますが、今回のこの私たちの「冒険的な試み」は今日のプログラムの「音楽の目的」に対する一つの方向だと思っています。またそれが良い方向になるだろうとも信じています。何しろ、フォルテピアノの通奏低音による演奏というのは困難を極めもしましたが、それにもましてリハーサルの度に新たな発見がありました。前述のクレメンティの「ピアノ演奏の手引き」の中に、「目的を追求して苦労したああとであらゆる困難を乗り越えそして輝かしい完成に達した生徒」の話がありますが、まさにその感がします。禅問答のようなプログラムノートになってしまいましたが、ここまで読んでいただいた方には大変感謝をいたします。また実際の演奏の時にはこんなことは全部忘れて音楽そのものを楽しんでいただければ幸いです。
ますと、彼らは限りないダイナミックスを手段としたかった。鍵盤楽器としてクラヴィコードはその要求を十分に満たした。と言うことは、彼らはその効果というものをよくわかっていた。しかし実際の演奏の場では、特に他の旋律楽器と一緒に演奏するのはあまりの小さい音のため現実的ではなかった。かと言ってそのころのフォルテピアノはまだちょっと実用的ではなかった。結果、ダイナミックスの効果を十分意識して作曲をしたが、実際の演奏の場ではチェンバロを使用するのがその時点では最良の選択だった。そう、もうほんの10年か20年後なんですが、十分実用になるフォルテピアノが作られるようになるのは1780年代になってからといわれています。
さてようやく冒頭の「音楽の目的」に戻りますが、今回のこの私たちの「冒険的な試み」は今日のプログラムの「音楽の目的」に対する一つの方向だと思っています。またそれが良い方向になるだろうとも信じています。何しろ、フォルテピアノの通奏低音による演奏というのは困難を極めもしましたが、それにもましてリハーサルの度に新たな発見がありました。前述のクレメンティの「ピアノ演奏の手引き」の中に、「目的を追求して苦労したああとであらゆる困難を乗り越えそして輝かしい完成に達した生徒」の話がありますが、まさにその感がします。禅問答のようなプログラムノートになってしまいましたが、ここまで読んでいただいた方には大変感謝をいたします。また実際の演奏の時にはこんなことは全部忘れて音楽そのものを楽しんでいただければ幸いです。